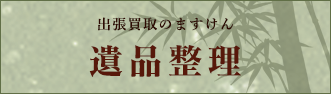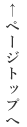コラム
-
人間国宝
魚住の砂張を継承 三代魚住為楽2017/12/18

銅鑼制作のパイオニアとして名を馳せた初代魚住為楽。その貴重な技と心構えを余すことなく受け継いだ三代魚住為楽は、詰襟の学生服の高校時代から祖父に師事し、さらに茶の湯の師匠にもついて茶道を学びました。初代が確立した砂張鋳造技術を正確に継承し、茶席で用いられる銅鑼や茶道具など、数々の名品を発表していある石川県を代表する名工です。
初代に技術を学ぶ
三代魚住為楽は1937年、魚住幸平の長男 として石川県金沢市に生まれました。父幸平は初代魚住為楽の長男で、銅鑼作りの全てを受け継ぐはずでしたが、1944年に戦死。初代は幸平に代わって三代に全てを託す事を決め、三代が高校生の時に銅鑼作りや鋳金の技術を教えました。厳しい修行により三代は砂張鋳造技術を習得すると同時に、茶の湯の師匠にもついて茶道を学び、茶道の精神や作法はもとより、銅鑼や水指などの茶道具の知識を深めました。この事が後の人間国宝三代魚住為楽の作家人生において、銅鑼だけでなく水指や茶道具を多く手掛けるきっかけとなりました。
として石川県金沢市に生まれました。父幸平は初代魚住為楽の長男で、銅鑼作りの全てを受け継ぐはずでしたが、1944年に戦死。初代は幸平に代わって三代に全てを託す事を決め、三代が高校生の時に銅鑼作りや鋳金の技術を教えました。厳しい修行により三代は砂張鋳造技術を習得すると同時に、茶の湯の師匠にもついて茶道を学び、茶道の精神や作法はもとより、銅鑼や水指などの茶道具の知識を深めました。この事が後の人間国宝三代魚住為楽の作家人生において、銅鑼だけでなく水指や茶道具を多く手掛けるきっかけとなりました。
高度な技術を正確に継承
 1964年、三代が27歳の時に初代が亡くなると、それまで銅鑼制作の第一人者であり名人といわれた師がいなくなり、三代にとって苦難の時代が始まります。銅鑼の姿形は立派に作れても、初代のように良い音が中々出せなかった為、とにかく初代から習った複雑な制作工程を繰り返し行い、数を作って体で覚えました。しかし、銅鑼作りの工程のひとつの「蝋貼り」という工程は、蝋の固まり具合が適した5月と10月にのみ行える為、一年を通して制作できる銅鑼の数も限られてしまいます。三代自身が納得のいく音色が完成するまで、気の遠くなるような年月がかかりました。こうして長年の経験と実績を持って作られる三代為楽の銅鑼は、深い余韻を残す事が特色となり、茶事を演出するのに相応しいとして高い評価を受けるようになりました。そして2002年65歳の時に、重要無形文化財「銅鑼」技術保持者として認定されました。
1964年、三代が27歳の時に初代が亡くなると、それまで銅鑼制作の第一人者であり名人といわれた師がいなくなり、三代にとって苦難の時代が始まります。銅鑼の姿形は立派に作れても、初代のように良い音が中々出せなかった為、とにかく初代から習った複雑な制作工程を繰り返し行い、数を作って体で覚えました。しかし、銅鑼作りの工程のひとつの「蝋貼り」という工程は、蝋の固まり具合が適した5月と10月にのみ行える為、一年を通して制作できる銅鑼の数も限られてしまいます。三代自身が納得のいく音色が完成するまで、気の遠くなるような年月がかかりました。こうして長年の経験と実績を持って作られる三代為楽の銅鑼は、深い余韻を残す事が特色となり、茶事を演出するのに相応しいとして高い評価を受けるようになりました。そして2002年65歳の時に、重要無形文化財「銅鑼」技術保持者として認定されました。
銅鑼制作の他には、金属の中で最も硬くて扱いにくいとされる砂張を使った水指や建水、蓋置、花入のほか、仏鈴なども制作。古来、渋い色合いと特別な味わいをもつ砂張の茶道具は愛好されていますが、初代為楽、三代為楽と受け継がれてきた砂張鋳造技術は「魚住の砂張」と名声が高く、三代自身も多くの名品を手掛けました。
古美術ますけんでは「三代魚住為楽」の作品の買取をしております。売却をご検討でしたらフリーダイヤル0120-134-003 又はフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。
新着コラム

2026/02/07陶磁器
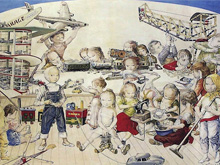
2026/02/06絵画

2026/02/05骨董

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
|
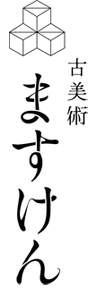

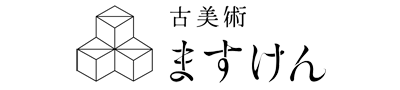
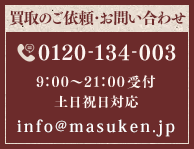

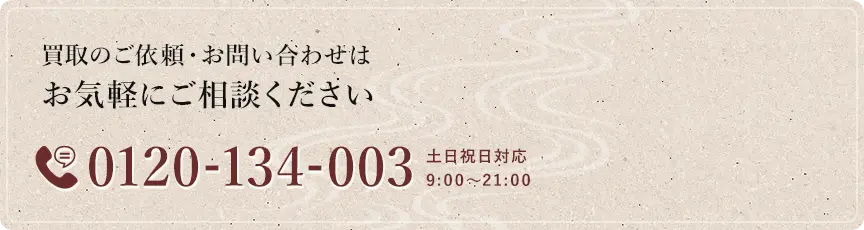
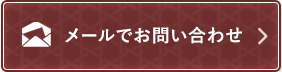
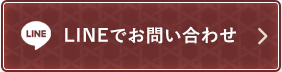

 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken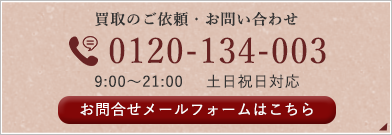
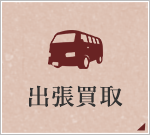
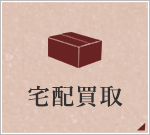

 一括買取対応
一括買取対応 豊富な販路
豊富な販路 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧