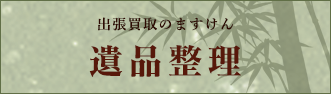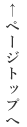コラム
-
人間国宝
歌人としても活躍 鋳金界の重鎮 香取秀真2017/09/18

「あづさゆみ はるとしるかに鉢植の 梅花もたす 芽をふきにけり」
正岡子規の門下で短歌を学び、隣人の芥川龍之介からは「お隣の先生」と呼ばれる異色の鋳金家、香取秀真。上の歌は春の到来をおのずと知る梅の花を情緒豊かに歌ったもので、工芸家でありながらも短歌や古代に造詣の深い文化人としての香取秀真の一面を伺い知ることができます。
古代への憧れ
香取秀真は幼い頃より古代に深い関心を 抱いていました。理由はいくつかあり、一つは5歳で千葉県佐倉の麻賀多神社の宮司の養子となり、風習や行事など伝統的なものを常に身近に感じていた事。もう一つは青年期まで過ごした佐倉には遺跡や古い寺院が多く、仏像を間近でみる機会に恵まれた事。そして佐倉集成学校に在学中に和歌に出会い自らも和歌を作るようになったことです。
抱いていました。理由はいくつかあり、一つは5歳で千葉県佐倉の麻賀多神社の宮司の養子となり、風習や行事など伝統的なものを常に身近に感じていた事。もう一つは青年期まで過ごした佐倉には遺跡や古い寺院が多く、仏像を間近でみる機会に恵まれた事。そして佐倉集成学校に在学中に和歌に出会い自らも和歌を作るようになったことです。
こうした古代への関心がピークとなった青年期、その情熱は「自らの手で昔から作られていたような仏像を制作してみたい」と思うようになります。そんな仏師を目指す秀真の背中を押したのは、秀真の類まれな素質を見守ってきた養父でしかも神社の宮司である郡司秀綱でした。秀綱は代々所有してきた土地を売却して秀真の上京に必要な資金を準備しました。それほど秀真の将来性を見込んでいたのでしょう。1891年、秀真は東京美術学校に首席で合格。当初は木彫りを学ぶために東美校に入りましたが、東大寺の大仏がどのようにして鋳られたのかを研究するため、金工に転向。1897年東京美術学校鋳金科を卒業し、晴れて鋳金家となりました。(昭和12年に『東大寺大仏の鋳造について』という本を出版し、研究結果を報告しています。)
工芸家初の文化勲章
 卒業の翌年は佐倉市の旅館の娘たまと結婚し翌年長男香取正彦が誕生。秀真24歳の時でした。その後もパリ万国博覧会など多数の展覧会で受賞するなど、華々しく活躍。しかし、若くして家族と弟子達を抱えた生活は実際には苦しく、極貧生活に耐えかねた妻が帰郷してしまう事態にまで見舞われてしまいました。それでも秀真は日本・中国の鋳金史の研究・制作を続け、1933年に東京美術学校教授となり、40年もの間、母校で「鋳金史」や「彫金史」の講義を続けました。その間、制作の方でも技術を高め、1934年帝室技芸員となり、1953年には美術工芸家として初となる文化勲章を受章しました。
卒業の翌年は佐倉市の旅館の娘たまと結婚し翌年長男香取正彦が誕生。秀真24歳の時でした。その後もパリ万国博覧会など多数の展覧会で受賞するなど、華々しく活躍。しかし、若くして家族と弟子達を抱えた生活は実際には苦しく、極貧生活に耐えかねた妻が帰郷してしまう事態にまで見舞われてしまいました。それでも秀真は日本・中国の鋳金史の研究・制作を続け、1933年に東京美術学校教授となり、40年もの間、母校で「鋳金史」や「彫金史」の講義を続けました。その間、制作の方でも技術を高め、1934年帝室技芸員となり、1953年には美術工芸家として初となる文化勲章を受章しました。
戦後は長男正彦とともに、戦時中に失われた寺院の梵鐘の復元に努めた香取秀真。豊かな技術を駆使した古典的な作品は品格高く、「という信念を最後まで貫きました。
新着コラム

2026/02/13絵画

2026/02/12骨董

2026/02/07陶磁器
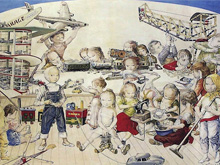
2026/02/06絵画

2026/02/05骨董
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
|
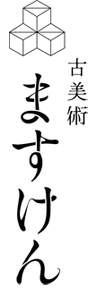

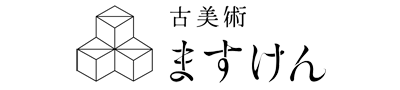
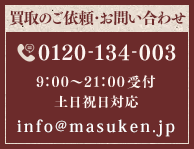

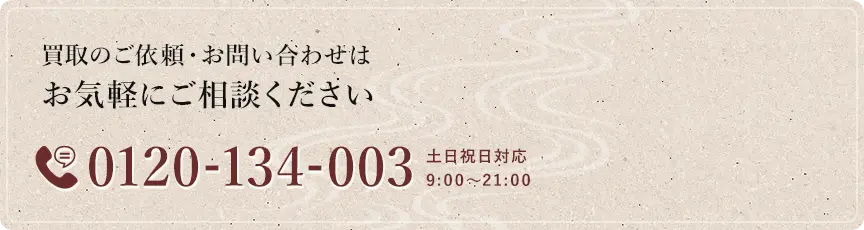
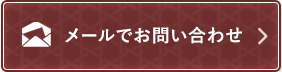
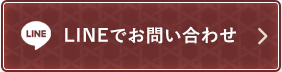

 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken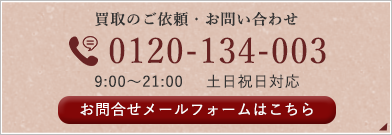
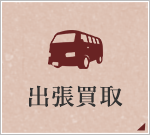
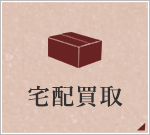

 一括買取対応
一括買取対応 豊富な販路
豊富な販路 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧