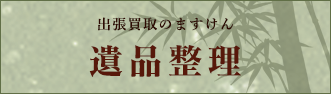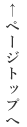-
人間国宝
試行錯誤から生まれた釉裏金彩 吉田美統2017/05/01

釉裏金彩とは、陶磁器の素地に意匠に合わせて切った金箔を貼りつけ、これを焼き付けた上に、さらに釉薬を掛けて焼き上げる制作技法です。1961年に金沢の陶芸家、武田有恒が第8回日本伝統工芸展に出品した「沈金彩鉢」が、陶器における釉裏金彩として最も早く、翌年第9回同展に重要無形文化財「色絵磁器」の保持者加藤土師萌がこの技法による作品を発表しました。この加藤の作品に感銘を受け、その技法を徹底的に研究・制作し、日本で初めて「釉裏金彩」で重要無形文化財に指定された陶芸家が、石川県出身の吉田美統です。
釉裏金彩との出会い
吉田美統は1932年、石川県小松市の九谷製造を家業とする 窯元錦山窯に生まれました。高等学校在学中より、同窯の職人から九谷焼の陶芸技法を学びました。1951年昭和26年に錦山窯3代目を継ぎ、上絵付や金襴手の伝統的手法を学びました。
窯元錦山窯に生まれました。高等学校在学中より、同窯の職人から九谷焼の陶芸技法を学びました。1951年昭和26年に錦山窯3代目を継ぎ、上絵付や金襴手の伝統的手法を学びました。
錦山窯は祖父の代から続く九谷焼の窯元で、父清一は赤絵金襴手を得意としており、吉田も当初から金彩に強い意欲をもって陶業に励んでいました。そうした中、やはり金襴手に秀作を多く残した加藤土師萌の遺作展で目にした釉裏金彩の作品に大きな触発を受け、この技法に生涯をかけて取り組む事になりました。
数々の試行錯誤から生まれた技法
 釉裏金彩に挑むようになった当初は、ごく薄い金箔から精細な文様を切り抜くことは困難でした。それもそのはず、当時は誰もが金箔を直線で切る技術しか持っていなかったので、金箔を全面に貼った上に色絵を施すか、幾何学模様の器が主流だったのです。しかし、吉田は紙で金箔を挟み込み、鋏も手の動きが直に伝わるドイツ製の医療用のものと使うことで、文様にあわせた自在な箔切りを可能にしました。また、金箔の厚さを3枚分のものや5枚分のものなどを特別に注文し、厚みの差によって生まれる釉裏金彩の新たな表現領域を広げました。それが可能だったのは、吉田の住む石川県の県都金沢が、国内の金箔の95%以上を生産する産地で、こうした注文に応える職人がいたことが幸いしました。
釉裏金彩に挑むようになった当初は、ごく薄い金箔から精細な文様を切り抜くことは困難でした。それもそのはず、当時は誰もが金箔を直線で切る技術しか持っていなかったので、金箔を全面に貼った上に色絵を施すか、幾何学模様の器が主流だったのです。しかし、吉田は紙で金箔を挟み込み、鋏も手の動きが直に伝わるドイツ製の医療用のものと使うことで、文様にあわせた自在な箔切りを可能にしました。また、金箔の厚さを3枚分のものや5枚分のものなどを特別に注文し、厚みの差によって生まれる釉裏金彩の新たな表現領域を広げました。それが可能だったのは、吉田の住む石川県の県都金沢が、国内の金箔の95%以上を生産する産地で、こうした注文に応える職人がいたことが幸いしました。
さらに、従来の金襴手は手ずれなどによって摩耗してしまうことが難点でしたが、吉田は色釉をかけて一度焼成し、その後箔を置き、その上に透明釉を掛けることで、その難点を克服するとともに、箔本来の輝きを保つ事に成功しました。
こうして様々な試行錯誤の末に生まれた吉田独自の釉裏金彩は、多くの人を魅了し、2001年には重要無形文化財釉裏金彩の保持者として認定されました。
陶芸界の中でも比較的新しい技法ではありますが、数々の伝統が紡がれて生み出されたこの釉裏金彩は、現代の陶芸表現に新たな表現領域を確立したのでした。
新着コラム

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

2023/02/20陶磁器

2023/02/01中国美術
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
|
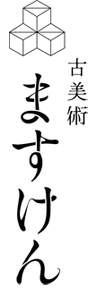

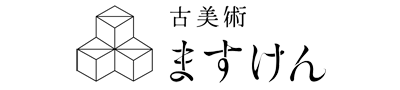
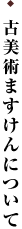
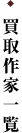
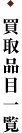
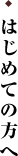
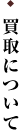
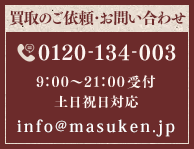
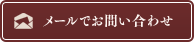
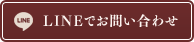





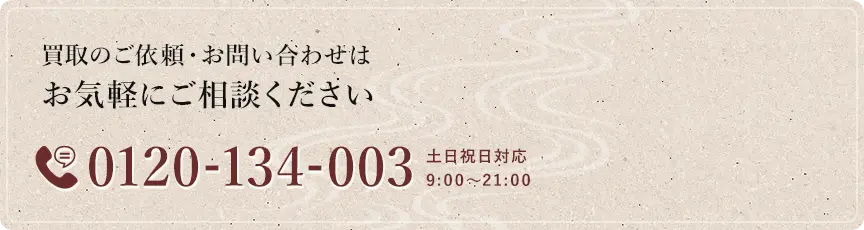
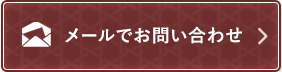
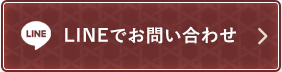

 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken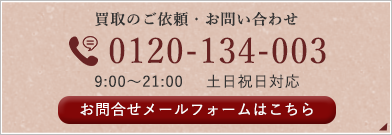
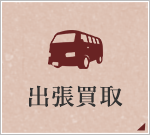
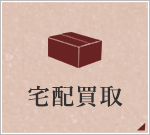

 一括買取対応
一括買取対応 豊富な販路
豊富な販路 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧