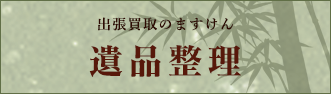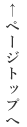-
人間国宝
一度は途絶えた濁手を継承 十四代酒井田柿右衛門2016/11/21

江戸時代初期、肥前有田の陶工「初代酒井田柿右衛門」は日本で初めて磁器の上絵付に成功したと伝えられています。その後初代柿右衛門の晩年には「濁手」と呼ばれる乳白色の素地が作られるようになり、これに優美な上絵付を施した柿右衛門様式が元禄頃にかけて完成されました。
しかしこの「濁手」。従来の青味がかった磁器の色に対し、米の研ぎ汁のようにやわらかみのあるミルキーホワイトに仕上げるには大変な手間と労力を要します。
高度過ぎる技法「濁手」
まず濁手に使われる土ですが、有田町内にある泉山、白川、岩谷川内の3種の陶石が6:3:1の割合で調合されています。しかしこの土は粘着力がないので轆轤が引きにくく、成形した後は天日干しでは割れやすい為、時間をかけて陰干しなくてはなりません。
次に焼成。温度調節が非常に難しい上、陶石の収縮率の違いによって破損が多いという難点があります。素焼きで10個のうち3・4個、本焼きで1・2個残れば良い方だといわれています。
すべての工程において非効率、且つ高水準の技術を要する為、「濁手」の技法は江戸中期にはあえなく途絶えてしましました。
濁手の復活
 こうして一度は途絶えた「濁手」を現代に甦らせたのが十二代柿右衛門と、息子である十三代柿右衛門です。二人は断絶していた濁手素地の復元に苦労を重ね、1953年に完全な復元に成功しました。
こうして一度は途絶えた「濁手」を現代に甦らせたのが十二代柿右衛門と、息子である十三代柿右衛門です。二人は断絶していた濁手素地の復元に苦労を重ね、1953年に完全な復元に成功しました。
柿右衛門濁手の製陶技術は、1971年1月に11名の上級技術者を会員として柿右衛門製陶技術保存会が設立され、1971年4月には重要無形文化財「柿右衛門(濁手)」として総合指定されました。
濁手の技術を継承した十四代
十三代の逝去により十四代酒井田柿右衛 門を継承したのが、十三代の長男、酒井田正でした。多摩美術大学で日本画を学び、伝来の製陶技術を祖父や父から習得し、1982年に十四代を襲名しました。絵付けを得意とした祖父・十二代からは絵の具の調合と絵付け法を、轆轤が達者な父十三代からは素地の調整・成形、その焼成法を受け継ぎました。特に柿右衛門赤絵の伝統を堅持する祖父から伝習を受けた事は、大変意義深く幸いな事でした。
門を継承したのが、十三代の長男、酒井田正でした。多摩美術大学で日本画を学び、伝来の製陶技術を祖父や父から習得し、1982年に十四代を襲名しました。絵付けを得意とした祖父・十二代からは絵の具の調合と絵付け法を、轆轤が達者な父十三代からは素地の調整・成形、その焼成法を受け継ぎました。特に柿右衛門赤絵の伝統を堅持する祖父から伝習を受けた事は、大変意義深く幸いな事でした。
地元佐賀の山々に自生する野の草花などのモチーフを積極的に取り入れた新しいデザインは、余白を生かし赤を基調とする伝統的な柿右衛門様式の作調によく合致し、2001年には重要無形文化財「色絵磁器」の保持者に認定されました。
2013年に癌の為亡くなりましたが、濁手と赤絵の伝統は、十五代酒井田柿右衛門によって守らています。
新着コラム

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

2023/02/20陶磁器

2023/02/01中国美術
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
|
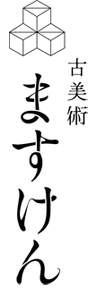

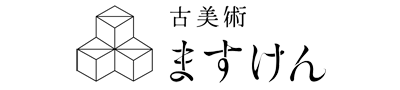
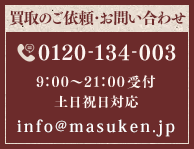


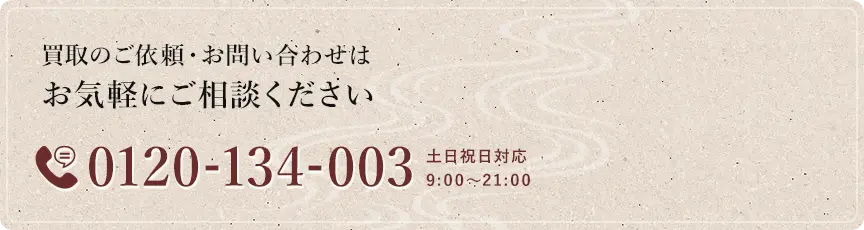
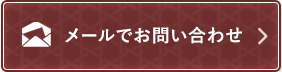
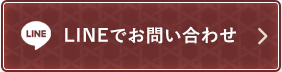

 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken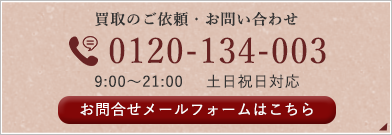
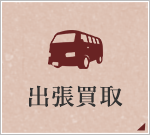
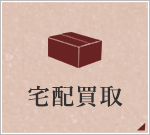

 一括買取対応
一括買取対応 豊富な販路
豊富な販路 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧